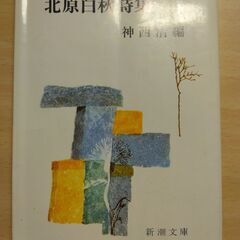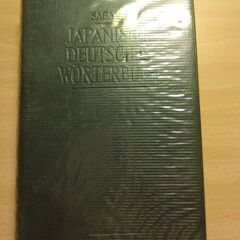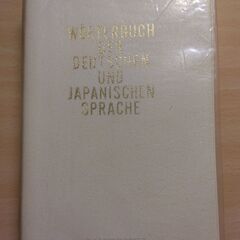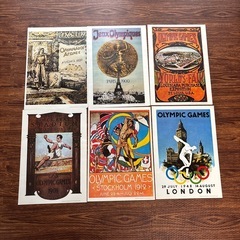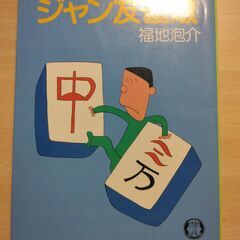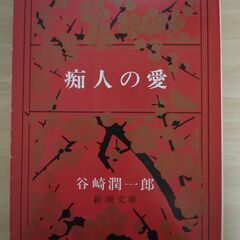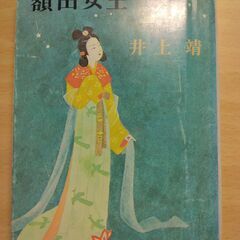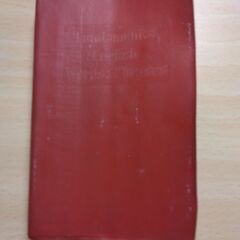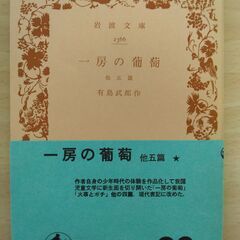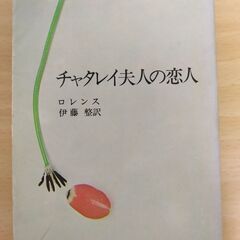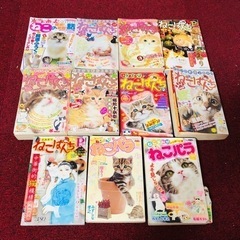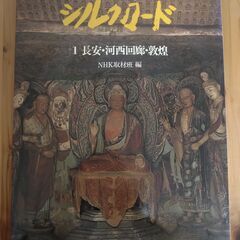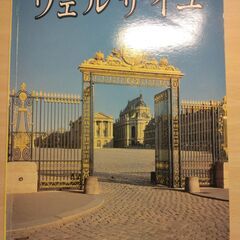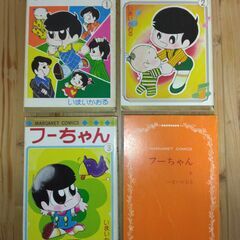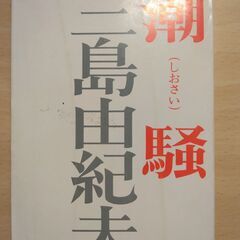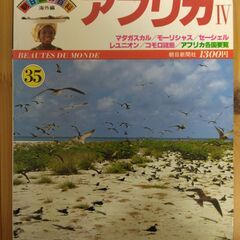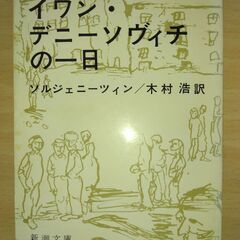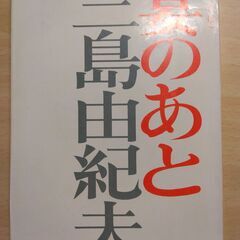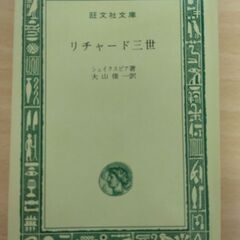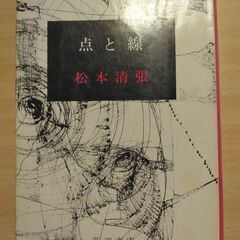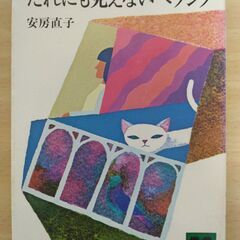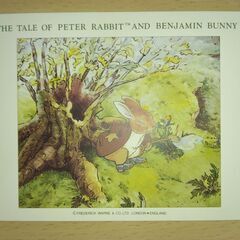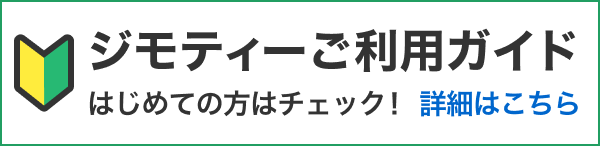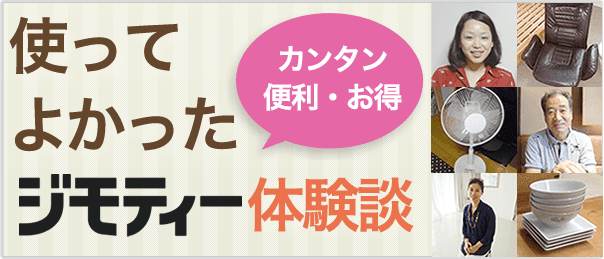『蟹工船・党生活者』小林多喜二 角川文庫(投稿ID : 1jzro6)
カバーの背部分に破れがあります。(写真③) 小口部分に日焼けがあります。(写真④) 50年以上前の発刊です。全体的にくすみがあります。(写真⑤) 『蟹工船・党生活者』 小林多喜二:著 角川文庫 昭和48年 15版 縦:15cm 横:10.5cm 厚さ:1cm フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より 『蟹工船』は、文芸誌『戦旗』で1929年(昭和4年)に発表された小林多喜二の小説である。いわゆるプロレタリア文学の代表作とされ、国際的評価も高く、いくつかの言語に翻訳されて出版されている。1929年3月30日に完成し、『戦旗』5月号・6月号に発表。「昭和4(1929)年上半期の最高傑作」と評された。『蟹工船』の初出となった『戦旗』では検閲に配慮し、全体に伏字があった。6月号の編が新聞紙法に抵触したかどで発売頒布禁止処分。1930年7月、小林は『蟹工船』で不敬罪の追起訴となる。作中、献上品のカニ缶詰めに対する「石ころでも入れておけ! かまうもんか!」という記述が対象であった。戦後1968年、ほぼ完全な内容を収めた『定本 小林多喜二全集』(新日本出版社)が刊行された。この小説には特定の主人公がおらず、蟹工船にて酷使される貧しい労働者達が群像として描かれている点が特徴的である。蟹工船「博光丸」のモデルになった船は実際に北洋工船蟹漁に従事していた博愛丸(元病院船)である。 あらすじ 「おい地獄さ行(え)ぐんだで!」 蟹工船とは、戦前にオホーツク海のカムチャツカ半島沖海域で行われた北洋漁業で使用される、漁獲物の加工設備を備えた大型船である。搭載した小型船でたらば蟹を漁獲し、ただちに母船で蟹を缶詰に加工する。その母船の一隻である「博光丸」が本作の舞台である。蟹工船は「工船」であって「航船」ではないため、航海法は適用されず、危険な老朽船を改造して投入された。また工場でもないことから、労働法規も適用されなかった。そのため、蟹工船は法規の空白域であり、海上の閉鎖空間である船内では、東北一円の貧困層から募集した出稼ぎ労働者に対する資本側の非人道的酷使がまかり通っていた。また北洋漁業振興の国策から、政府も資本側と結託して事態を黙認する姿勢であった。情け知らずの監督である浅川は労働者たちを人間扱いせず、彼らは劣悪で過酷な労働環境の中、暴力・虐待・過労や病気で次々と倒れてゆく。ある時転覆した蟹工船をロシア人が救出したことがきっかけで、労働者達は異国の人も同じ人間と感じるようになり、中国人の通訳も通じ、「プロレタリアートこそ最も尊い存在」と知らされるが、船長がそれを「赤化」とみなす。学生の一人は現場の環境に比べれば、ドストエフスキーの「死の家の記録」の流刑場はましなほうという。当初は無自覚だった労働者たちはやがて権利意識に覚醒し、指導者のもとストライキ闘争に踏み切る。会社側は海軍に無線で鎮圧を要請し、接舷してきた駆逐艦から乗り込んできた水兵にスト指導者たちは逮捕され、最初のストライキは失敗に終わった。労働者たちは作戦を練り直し、再度のストライキに踏み切る。 『党生活者』は小林多喜二の小説。作者没後の1933年、『中央公論』の4月号と5月号に発表された。 あらすじ 東京にある「倉田工業」では、パラシュートやガスマスクの部品などの軍需品を作っていた。「私」は、そこに臨時工としてつとめながら、工場の中に党組織をつくろうとしていた。ある日「私」は太田という自分のことをよく知っている同志が検挙されたことを知り、工場に出ることができなくなる。そこで「私」は、運動に協力的だった女性、笠原と共同生活をしながら、工場に残った須山や伊藤などの同志とともに、工場の中で戦争反対の動きをつくろうとする。しかし笠原との生活にはきしみが生じるし、倉田工業のなかで戦争反対のビラをまくことに成功はしたが、須山も伊藤も工場を追われてしまう。そんな中でも「私」も含めたみんなはあたらしい運動の場をつくろうと努力を続けていく。
文芸(本/CD/DVD)の売ります・あげますの関連記事
『蟹工船・党生活者』小林多喜二 角川文庫 高知 中古あげます・譲りますを見ている人は、こちらの記事も見ています。