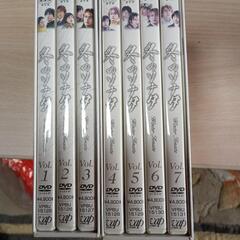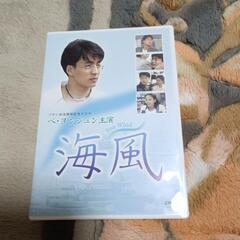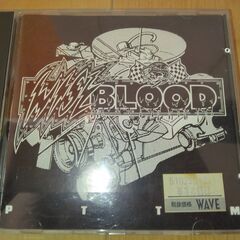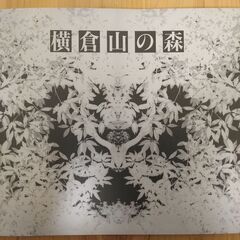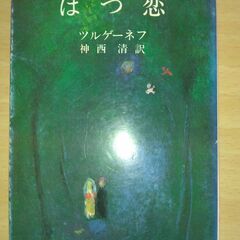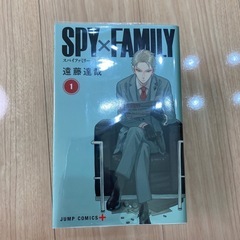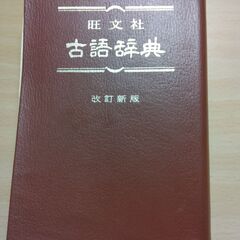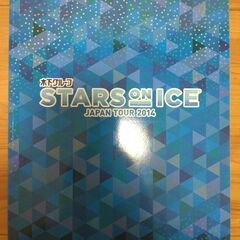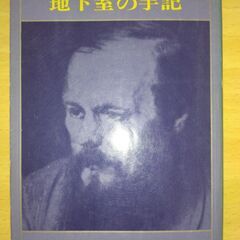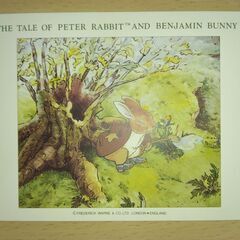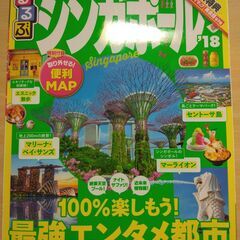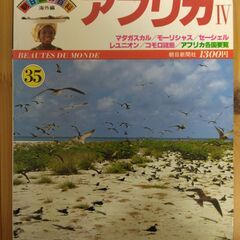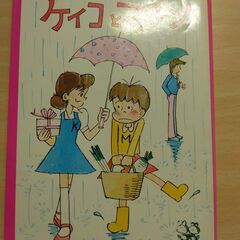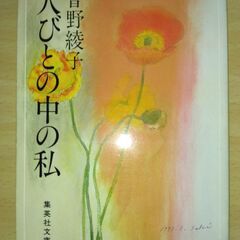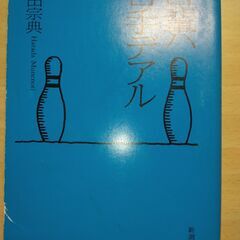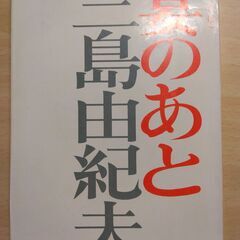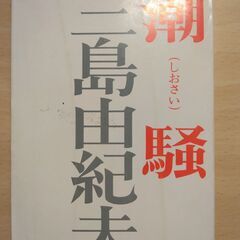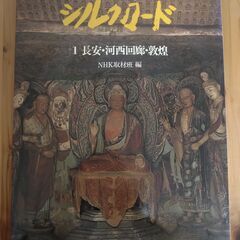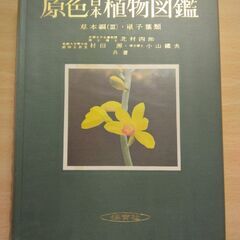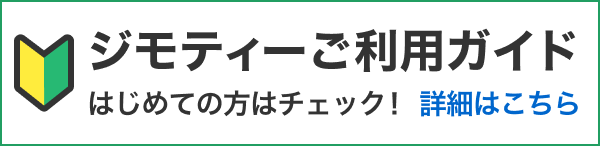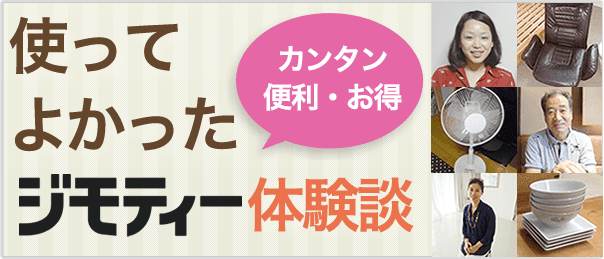『若山牧水歌集』若山喜志子選 岩波文庫(投稿ID : 1i70uv)
『若山牧水歌集』 若山喜志子:選 岩波文庫 1985年 第51刷 縦:15cm 横:10.5cm 厚さ:1.2cm フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より 若山 牧水(1885年(明治18年)8月24日-1928年(昭和3年)9月17日)は、戦前日本の歌人。本名・繁。 自作の短歌の揮毫を多数制作しており、書家としても知られる。 旅を愛し、生涯にわたって旅をしては各所で歌を詠み、日本各地に歌碑がある。 鉄道旅行を好み、鉄道紀行の先駆といえる随筆も残している。 大変な酒豪(またはアルコール依存症)としても知られ、1日に1升の酒を飲んでいたという。死因は肝硬変である。盛夏に死亡したにもかかわらず、死後しばらく経っても遺体から死臭がせず「生きたままアルコール漬けになったのでは」と医師を驚かせた逸話がある。 自然を愛し、特に終焉の地となった沼津では千本松原や富士山を愛し、千本松原保存運動を起こしたり、富士の歌を多く残すなど、自然主義文学としての短歌を推進した。 情熱的な恋をしたことでも知られており、妻・喜志子と知り合う前の園田小枝子との熱愛を詠んだ歌も残る。 出身地・宮崎県では牧水の功績を称え、1996年(平成8年)より毎年、短歌文学の分野で傑出した業績を挙げた者に「若山牧水賞」を授与している。 牧水自身は宮崎県出身だが、祖父・若山健海は武蔵国神米金村(現・埼玉県所沢市神米金)出身で、長崎にて西洋医学を学び、宮崎県にて診療所を営む開業医であった。 牧水は祖父ゆかりの地である埼玉県を度々訪れた。大学時代には所沢を訪れた。所沢市の八雲神社には、牧水の歌碑が建立されている。また、秩父地方にも数度訪れて、歌と紀行文を残している。秩父市の羊山公園には「牧水の滝」と名づけられた滝があり、そこには 「秩父町出はづれ来れば機をりのうたごゑつゞく古りし家竝に」という秩父の春を歌った碑がある。 代表歌 幾山河越えさり行かば寂しさの終てなむ国ぞ今日も旅ゆく 白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ うら恋しさやかに恋とならぬまに別れて遠きさまざまな人 ※配送をご希望の場合、配送料は215円です。 ※複数の購入を検討いただける場合、配送料が変わる可能性がございます。お気軽にお問い合わせください。
文芸(本/CD/DVD)の売ります・あげますの関連記事
『若山牧水歌集』若山喜志子選 岩波文庫 高知 中古あげます・譲りますを見ている人は、こちらの記事も見ています。