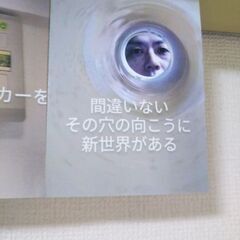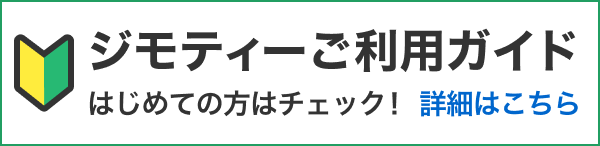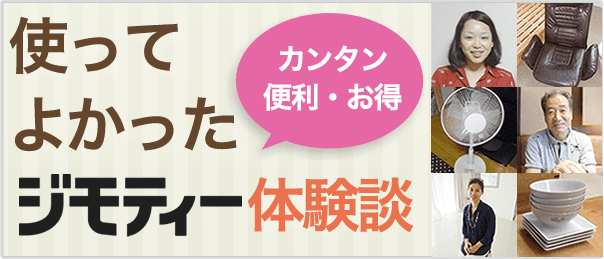ようやく理解できていません。
磁界について。
光の屈折について。
世の中にある、電荷の動きが磁界をつくるという説明から、以下を思い浮かべました。
磁界そのものについて、書かれていません。
なので、ちんぷんかんぷんな説明になっています。
説明ではなく、想像です。
観察はしていません。
それが、以下の括弧内です。
「光の屈折について。
磁界の方向に平行にならない角度で磁界に進入してきた荷電粒子。
負の荷電粒子は進行方向から見て、右回りに磁界を作ります。
霜箱実験にて、確認できます。
磁束密度が高い、または低い方ができます。
磁界に進入してきた荷電粒子を、中心として。
磁束を発生させる、動く荷電粒子そのものを、荷電粒子周囲の磁束密度の高低が、押すのです。
磁束密度の低い方へ。
低速領域に最初に入り込んだ荷電粒子の列の一番端の粒子。
低速領域に入り込めば、動きが、遅くなります。そして、その動きと同時に発生する磁束の発生も、遅くなります。
角度を持って、低速領域に入り込んだとしましょう。
荷電粒子の左側から、入るような場合。
荷電粒子の反対側は、まだ低速領域に入っていません。
そして、その荷電粒子の列には右側には、まだ低速領域に入っていない荷電粒子が横一列に並んでいます。
みな、磁束をうみだしています。
左側だけ、低速領域に入った荷電粒子は、その右隣の磁束の影響を受けます。
右側の方が、磁束密度が一瞬、高くなります。
左側の方が、磁束があらわれる速度が遅くなっているから。
その結果として、一番左端の、左側だけ低速領域に入っている荷電粒子は、右側から押されます。
つまり、左に押されます。」
先日、舟にのる機会がありました。
舟から見る海面を思い浮かべて、想像し直しました。
それが、以下の、ますますわかりにくい文です。
電荷を押す頻度。
頻度が高まれば、感応する率も高くなる。
円弧上の感応する点数も増える。
屈折時、円弧上の感応する点数が多い方が大きく曲がるのは、短い間隔の点それぞれが各々、感応速度が遅くなる方へ偏るため。
例えば、半径10cmごとに。
例えば、半径1mmごとに。
既に遅くなった1点目。
その1点目に応じて偏った2点目。
その2点目の偏りに応じて偏る3点目。
今度は偏った2点目の速度が減速域に入り落ちる。
その2点目速度の、減速、に応じて、また3点目が偏る、
これがが短い間隔で続く方が、曲がりが大きくなる。
磁界とは電荷の偏りである。
それが円上に、より多く感応する点があるのは、感応させる因がより多いということ。
故に、円上に、多く存在する。
その因が多いことを、世の中では、周波数が高いという。
屈折について、説明しています。
世の中の磁界の説明に疑問を持ちました。
打ち消すようなという説明。
先日、舟にのる機会があったので、海面を思い浮かべて。
船に例える、ひとつの電荷。
その、ひとつの電荷が一筋に通る。
周囲の同じ電荷を、周囲に押しやる。
それが、同心円状にひろがっていく。
同じ方向に進む舟。
同じ方向に水を前方に押しやる。
水は、両船の間ではなく、両船の外を抜けていく。
すれ違う舟。
すれ違う舟それぞれの押す水が押し合う。
その水は両船の間に入り、両船を互いに脇腹から押す。
押されて偏る電荷の角度。
反発か、吸引か。
前方に電荷がなければ、前のめりになります。
前方がへこんでいれば、前方に吸い寄せられます。
前をゆく舟に近すぎすぎた舟。
最後尾のお尻に、両脇から入り込もうとする水。
お尻同士、突合せ。
突き合わされたお尻の両脇から、水が流れ込みます。
水で溢れ、お尻は水に押されて離れます。
しかし、磁界をこうとらえると、次の説明は、どうなるのか。
電子の動き。それが奥から手前に、一直線に向かってくる。
その動きの直線の周囲に磁界が生じる。
電子、つまり負の電荷であれば、右回りの磁界が生じる、という説明。
磁界を、電荷の偏りとして想像した上で、この右回りの磁界をどう説明しようかと想像しました。
負の電荷が、奥から手前に、一直線に、私に向かってきます。私の胸に、私の額に、私の正面めがけて向かってきます。
まるで、舟を後方から追いかけてくる、海鳥のごとく。
その、負の電荷は、傘をひらくがごとく、傘の円周上の頂点が、ひろがるごとく、まわりの同じ負の電荷を押しやります。
そうでしょうか。
ここで、傘のひろがるごとく、周囲の負の電荷を押しやるのかと思えば、そうではありません。
その理由を、想像しました。
例え話です。
例えば、仮の話として、弾かれた方に行くのは、長旅であります。長旅は重いです。
列車に乗って、東京から北海道まで行くのと、マンホールのまわりを自転車でぐるぐる回るのと、どちらが楽か。
マンホールのまわりをぐるぐるまわる方が楽です。
つまり、弾かれたその先にある、とこまでも連なる列車を押す、というのは重く、その列車の連なりが東京から北海道まで続いているとなれば、なおさらです。
この、押すのは重いので、軽い円を描く方へ逃れるという例を取り入れるとして、では何故、左へは逃れないのか。右へ逃れるのか。
ここで、電荷の軌跡の中心からそれを見ています。
進行方向に頭、軌跡の尾に体をそわせて。
そういう姿勢で見ています。
何故、右に動くのか、と。
一度浮いた電荷は、何か力をうけるのではないか。
例えば、pn接合のp側が、太陽の振動をうけると、炭素よりひとつ正の電荷の少ない核の電子対の、つまり、対応する正の電荷のない電子は浮き、浮いた下に他の電子が入りこみ、線でつながるp側への電子の移動により、より寄せつける力の明確になった、元いたn側へフロートする。
このような、何らかの機杼があると、想像します。
例えば、私は、いかんともしがたい尿意をもよおして、2部屋しかないアパートの、どの部屋へ行けば良いのでしょうか。
トイレですか?
リビングですか?
洗手間。
最近、duolingoアプリを用いています。
洗手間は、中国語でトイレのことです。
たいへん、良いアプリです。みなさんもダウンロードをしてみてください。
哲学 提言 (投稿ID : 1hjp2k)
更新2025年6月23日 00:13
作成2025年5月22日 07:17
その他の地元のお店の関連記事
哲学 提言 東京 広告の無料掲載 を見ている人は、こちらの記事も見ています。
-
 港区/大阪市📸民泊の写真、プロの視点からアドバイスし…
港区/大阪市📸民泊の写真、プロの視点からアドバイスし… -
 大田区/大…☆共同使用契約にもとづく個人間のカーシェ…
大田区/大…☆共同使用契約にもとづく個人間のカーシェ… -
 八王子市/…ジェルキャンドル作ります。 お打ち合わせ…
八王子市/…ジェルキャンドル作ります。 お打ち合わせ… -
 江東区/清…東京都内でアパレルのサンプル縫製・小ロッ…
江東区/清…東京都内でアパレルのサンプル縫製・小ロッ… -
![[個別指導] 運転仕方やポイントおしえます](https://cdn.jmty.jp/articles/images/6740865a16f3682bbaaf5fa8/thumb_m_file.jpg) 渋谷区/代…運転が上手くなりたい方の運転指導します …
渋谷区/代…運転が上手くなりたい方の運転指導します … -
 足立区/竹…初めまして。基工業と申します。 東京都…
足立区/竹…初めまして。基工業と申します。 東京都… -
 新宿区ご覧頂きありがとうございます。 現在BA…
新宿区ご覧頂きありがとうございます。 現在BA… -
 練馬区/下…6畳エアコン取付します。 大きめの 8.…
練馬区/下…6畳エアコン取付します。 大きめの 8.… -
 栄町/板橋区東京都板橋区内で、借り手が見つかってない…
栄町/板橋区東京都板橋区内で、借り手が見つかってない… -
 新宿区/飯…月額35,00円で、毎週月~金曜日迄のお…
新宿区/飯…月額35,00円で、毎週月~金曜日迄のお… -
 新宿区/大…【Sabori 公式サイト】 ご予約・…
新宿区/大…【Sabori 公式サイト】 ご予約・… -
 千代田区/…【Sabori 公式サイト】 ご予約:…
千代田区/…【Sabori 公式サイト】 ご予約:… -
 新宿区/大…★定期的に午前中実質無料キャンペーン実施…
新宿区/大…★定期的に午前中実質無料キャンペーン実施…