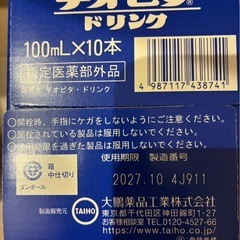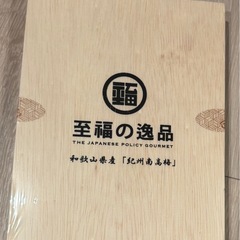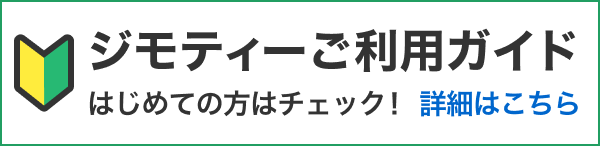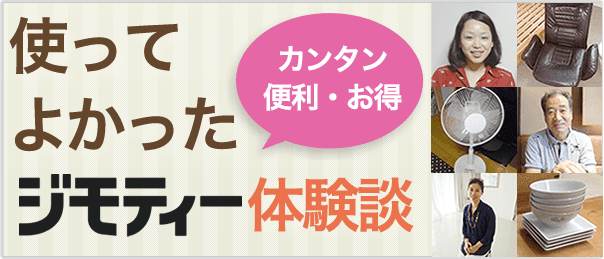【新米】長野県産コシヒカリ ハゼ掛け米 10kg(投稿ID : 1l4cu1)
【令和7年新米】 【長野県産】コシヒカリ はぜ掛け米 精米済み 白米 10kg ■商品説明 長野県産コシヒカリの令和7年新米です。 代々受け継いでいる田んぼで長年お米作りをしています。 コンバインではなく、手作業で「はぜ掛け」という稲を干す作業をされています。 そのため、大量生産は難しく、数量限定でのご案内となります。 数週間天日干しをすることで、よく乾燥し、美味しいお米ができます♪ 【~お米ができるまで~】 田んぼの状態を整え、田植をし、毎日田んぼの水の量をチェックし、 秋になると「稲刈り」を行って数週間稲を干します。 よく乾燥した稲を「稲こき」をしてお米のみにします。 そのお米を精米して、「新米」の出来上がりです♪ 【はぜ掛け米の特徴】 長年受け継がれてきた伝統製法「はぜ掛け(はさがけ)」でじっくりと天日乾燥させた、 農家の誇りそのもののようなお米です。 🌾 はぜ掛け米だけの格別な理由 ●太陽と風が育む、凝縮された旨味 刈り取った稲を束ね、木組みの「はぜ(稲架)」にかけ、約2~3週間かけて自然の力だけでゆっくりと乾燥させます。この間に、稲の茎に残った養分や旨味が、一粒一粒のお米にじっくりと行き渡ります。機械乾燥では決して出せない、ふくよかな甘みと深いコクが生まれます。 ●粘りとツヤが違う、感動の食感 太陽の光を浴びて熟成されたお米は、一粒一粒がしっかりとし、噛むほどに甘みが増します。炊きあがりのツヤ、立ち上がる豊かな香り、そして口の中で広がる粘りのバランスは、まさに絶品。冷めても硬くなりにくく、おにぎりやお弁当にも最適です。 ●希少性の高い、伝統の味 天候に左右され、また多大な労力と時間が必要な「はぜ掛け」は、今や大変希少な製法となりました。このお米は、「本当に美味しいお米を届けたい」という農家の熱い想いと、日本の美しい原風景を次世代に残すための努力の結晶です。 毎日食べるお米だからこそ、本物にこだわりたい。 数量限定の特別な逸品を、ぜひこの機会にご賞味ください。 あなたの食卓に、日本の伝統と太陽の恵みをお届けします♪ 🌾 新米をおいしく炊くための3つのポイント 1. お米の研ぎ方:手早く、やさしく 新米は粒がやわらかく、水を吸いやすいため、研ぎすぎると米が割れたり、ぬか臭さを吸い込んだりしてしまいます。 最初の水はすぐに捨てる: 最初に水を加えたら、軽く2~3回かき混ぜてすぐに水を捨てます。米粒がぬか臭い水を吸うのを防ぐため、この作業は手早く行います。 やさしく研ぐ: 少量の水を入れ、指を立てて円を描くようにやさしく20回ほど研ぎます。力を入れすぎず、米粒を傷つけないように注意します。 すすぎ: 濁りが少なくなったら、水を入れ替えて2~3回すすぎます。 2. 水加減:やや少なめに 新米はもともと水分を多く含んでいるため、通常のお米と同じ水加減だと、べたつきやすいご飯になってしまうことがあります。 基本は目盛り通り: 炊飯器の「白米」目盛りに合わせますが、お好みで目盛りより1~2mm、または1合あたり大さじ1杯(約15cc)ほど水を減らすと、よりふっくら、しゃきっとした仕上がりになります。 良質な水を使う: 炊飯に使う水(特に最初の吸水時)をミネラルウォーター(軟水)にすると、新米の風味がさらに引き立ちます。 3. 浸水時間:短め、または不要 最近の炊飯器は、炊飯工程に自動で浸水時間(吸水)が含まれているため、新米の場合は基本的に浸水は不要、または短時間で十分です。 炊飯器の場合: 研いだらすぐに炊飯器にセットし、「早炊きモード」で炊飯するのがおすすめです。高温で一気に炊き上げることで、ふっくらとしたご飯になります。 浸水させる場合: お好みの食感に応じて、30分〜1時間程度浸水させます。長すぎると米がふやけてべたつく原因になるため注意してください。 🍚 炊き上がり後の仕上げ 炊飯が完了したら、すぐに蓋を開けずに蒸らし、仕上げを丁寧に行うのが美味しくなる最後のコツです。 蒸らし(10分): 炊飯器によっては自動で蒸らし工程が入りますが、炊き上がりのブザーが鳴ってもすぐに蓋を開けず、10分ほど蒸らします。 ほぐし: 蒸らしが終わったら、しゃもじでご飯を潰さないよう、釜底から大きく十字に切り、全体をさっくりとほぐします。余分な水分を飛ばし、ご飯粒を立たせることで、ムラなくふっくらと仕上がります。 この方法で、新米ならではの瑞々しく、芳醇な香り高いご飯をぜひお楽しみください♪
食品の売ります・あげますの関連記事
【新米】長野県産コシヒカリ ハゼ掛け米 10kg... 長野 中古あげます・譲りますを見ている人は、こちらの記事も見ています。