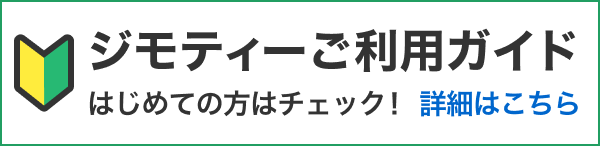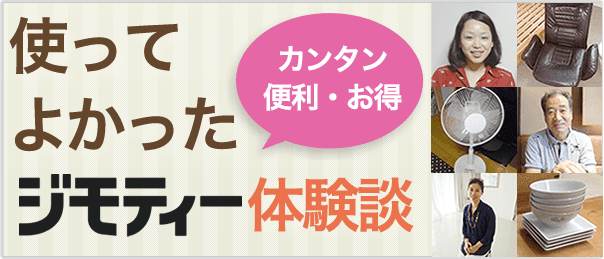令和7年産 発想の転換たにし活用で無農薬 玄米10kg 玄米10kg 玄米食にお勧めです(投稿ID : 1k59ys)
種子から収穫まで無農薬にこだわって栽培しておりますが有機認証は受けていません。有機栽培はずっと継続しており,ことさらに有機というラベル貼りにコストを掛けたくない思いからです。 1枚目の写真: 「れんげ農法」という昔から伝わる栽培方法で作ったお米です。5月初めの鋤込み前の田にはれんげ蜜を求めてミツバチが乱舞しています。「れんげ」の根のまわりには「根粒菌」があり、空気中の窒素を根に取りこんで、元肥とします。また「れんげ」が発酵することにより「土」を活性化させ、稲を自然のまま、元気に育てることが出来ます。この「れんげ」以外には肥料は使っていません。「れんげ」の種は毎年播きますが、5月に鋤込んだこぼれ種が稲の収穫時にはもう発芽していました。 2枚目の写真: 除草方法としては,手取り除草からあいがも農法を経て,西日本ではどこにでもいるジャンボタニシに注目しました。このタニシは田植え直後の稲苗を食べる害虫として嫌われています。でも稲苗も雑草も見境なくどん欲に食べます。そうだとするとみすみすこれを見逃すことはない!ここは発想を変えればいいんじゃないか。色々試行したり,人にも聞きました。(当方の独創ではありません。愛農学園創立者の小谷純一先生に負うところ大です。)そこでその習性を利用し,田の高低を均等にならした上で田植え直後には水深をゼロにして,1ケ月位かけてゆっくりと水面を上げるようにし,その間水田には故意に雑草を生やすように心掛けました。するとタニシは株元が堅くなっていく稲苗よりもその後に発芽してくる柔らかい雑草を好んで食べるではありませんか。この時間差に目を付けました。 これは株間ですが,普段は触角を出しながら田んぼの中をはい回るので栽培初期から雑草は全くと言っていいほどありません。(普通の栽培法では田植え直後浅水にすると雑草が繁茂するので深水にします。もしそこにタニシがいると水中では活発に動くので稲苗を食べます。だから害虫として嫌われます。でも体が水面上に出ると重い殻を背負っているのか動くのもままならないようです。そのため田植え直後には浅水状態を保ちます。ここが普通の栽培方法とは全く逆になり発想の転換が必要になります。) この写真は地面の雑草を食べつくした後垂れてきた枯れ葉に食いついてきたところです。この旺盛な食欲をご覧ください。左端は地面をはい回っている普段の状態です。豆粒みたいに全体に散らばっているのが生まれたばかりの子供です。 3枚目の写真: こうするとほぼ完璧と言えるほどに雑草退治は出来ます。わずかな例外ともいえるのは成長が早いヒエなどです。成長が早いのでタニシの食害を免れます。ヒエは稲とよく似ているので見分けにくいですが穂が出て見つけ次第種を落とさないように丹念に抜き去り,翌年度に持ち越さないようにすれば十分です)。ヒエ以外は実害があまりないので放置しています。コナギやオモダカという雑草に辟易している方もいますが,これらは軟弱雑草なので好んでジャンボタニシが片づけてくれます。 4枚目の写真: ただタニシ利用のこの方法は田の高低を均すのが一番肝要で,もし均すのが不十分だと窪みになったところにタニシが集まって苗を食べ荒らすという悪さをします。これがマスメディアでニュースになったりします。他方高いところへはタニシは行かず雑草だらけになります。この写真の上方はきれいに雑草を掃除してくれていますが,下方は雑草がいっぱいです。均すのが不十分だとこんな風になります。失敗例です。 無農薬栽培では雑草対策が一番大きな課題だと思います。農薬散布を単純に止めるのは至極簡単なことなんです。しかしそうすると雑草が繁茂し,養分や日光を雑草にとられ収量が激減します。そのため多くの人が除草剤を使うようになったのですが,環境ホルモンという形で深刻な弊害が出てくるようになりました。 (ジャンボタニシを除草に活用されている方も少数ですがおられますのでネットで検索してみてください。寒さに弱いので越冬できる西南暖地では多いようです。しかし総じて行政側は稲の敵とみて駆除対象と考えています。でも実際に除草に活用してみるとあいがもを使っていた頃に比べて非常に楽になりました。もうあいがも農法へ戻るつもりはありません。) しかしこのタニシは除草には効果的であっても病気や虫の害には役立ちません。じゃあ後は為すすべはないかと思っていたところ,農薬を撒かないものだからカマキリ,クモ,カエルなどの小動物たちが虫を捕るのに大活躍してくれていました。 5枚目の写真: カマキリです。獲物を捕食中は撮影できませんでしたが、このように稲穂の上を飛び回って獲物を捜しています。 6枚目の写真: 株間でクモが巣を張って,獲物が掛かるのをひたすら待っています。撮影のためそうッと近寄って撮影できました。 7枚目の写真: アマガエルで緑色が保護色となっています。カエルは肉食性で,小さな昆虫類が好きで動いているものに素早く反応し,飛びついて補食します。 8枚目の写真: クサガメです。田で生まれたばかりの子亀を発見。撮影のためたらいに移して撮影しました。大きくなれば田では繁殖力旺盛なジャンボタニシの天敵となって,タニシが増えすぎないように調節してくれます。これも近くの谷川から、迷い込んだ親から生まれたものでしょう。 このように様々な生き物達がいる環境では,それぞれが適度な緊張感を持っており,そのことが稲をも元気にしていると考えています。(無農薬栽培を長年続けていると病害虫による多少の被害はありますが、病害虫が大発生して収量激減するようなことは皆無でした。) またタニシやドジョウなどを狙って野生のマガモやシラサギなんかがよく飛来してきます。でもこれらはあいがも君みたいには働いてくれません。却って離着陸時に稲苗を倒したりして困る厄介者なんです。 そうすると病害虫対策は疎植にして風通しを良くし,イネ本来の体力ではね返してもらうしかないですね。それでも多少はやられます。(病弱な稲苗を助けて増収を図る事はしないというのを基本方針としています。) だからよく見ても解らない場合もありますがカメムシにやられた米などが残っている場合もありますし,白濁米もあります。これらは食味にはそう関係ないと思うのでそのままにしています。ただそればかりを集めてみると味は落ちるかも知れません。だから神経質な方は入札をご遠慮下さい。 でもこうなるとJAの検査では1等米にはしてくれません。ご存じないかも知れませんがJAの等級検査は見た目の外見だけで判定するんです。だからJAには出荷できません。検査米に通るには通常の栽培では殺虫剤等を頻繁に投与するか色彩選別するなどの見栄えをよくする何らかの対策をとっています。 そこで完璧な見た目のいい米が欲しい人は入札しないでください。生意気に思われるかも知れませんがそう言う人には買い上げて欲しくありません。却ってアトピーなんかに悩んでおられ,農薬なしで栽培した米の価値が分かってくれる人は大歓迎です。収穫後に色彩選別機を通しておりますが、完璧なものではありません。 9枚目の写真: ところで米の食味は使用する水にも左右されます。我が家の水田は中山間地区にあり,農業用水ではなく山腹から流れ出る谷川の水を使っています。その澄み切った谷川にはフナやオイカワ、メダカなどもよく目に付き,夏の夜には蛍も乱舞します。たまたま水の取り入れ口付近で多くのカワニナを発見しました。これはとんがり帽子に似た巻き貝で蛍の幼虫のえさとなります。田圃ではジャンボタニシの方が多いのですがカワニナも駆逐されてはいませんでした。ちなみにカワニナは水のきれいさを4段階で示す指標生物の2番目となる生物だそうです。 2018年度徳島県産の「あきさかり」が食味試験で初めて特Aを獲得したことから、次年度(2019年度)からJA徳島市の奨励品種となりました。試食してみたところ「あきさかり」が美味しかったし、栽培上の難点も少ない様なので、翌年から我が家でも「あきさかり」を栽培することになりました。2025年度産も食味は大変良く気に入っています。 残りの画像はメール添付で送れます。 送料は2000円となっておりますが、これは0~2000と書けなかったためです。2000円は上限額で、超える分についてはこちら持ちです。近いところは実際の送料との差額をお返しします。
食品の売ります・あげますの関連記事
令和7年産 発想の転換たにし活用で無農薬 玄米1... 徳島 中古あげます・譲りますを見ている人は、こちらの記事も見ています。