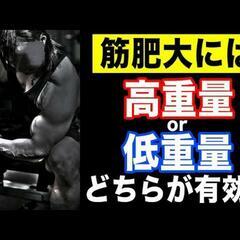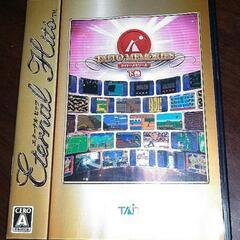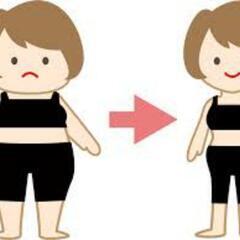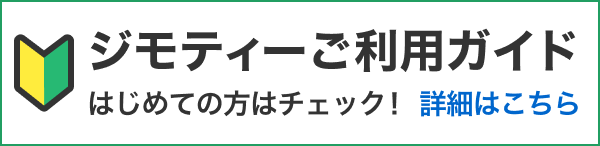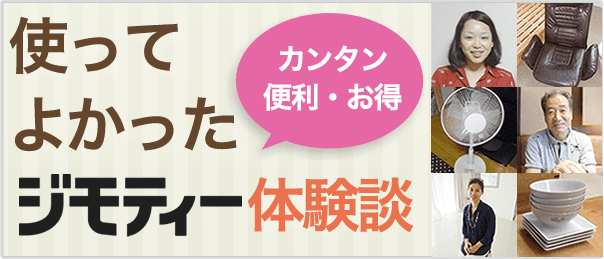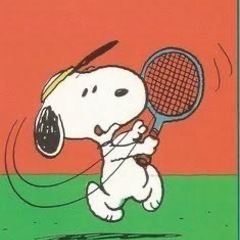 太田市/竜…こんにちは〜!!! 太田でバドミントンし…
太田市/竜…こんにちは〜!!! 太田でバドミントンし… 高崎市ソフトテニスを一緒に楽しめる仲間を募集し…
高崎市ソフトテニスを一緒に楽しめる仲間を募集し…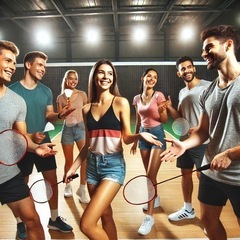 高崎市楽しく体を動かしたい方✨ 気軽にスポーツ…
高崎市楽しく体を動かしたい方✨ 気軽にスポーツ… 高崎市🎾 硬式・軟式テニスサークル メンバー募…
高崎市🎾 硬式・軟式テニスサークル メンバー募… 高崎市⚾️野球仲間大募集‼️ チームメンバー&…
高崎市⚾️野球仲間大募集‼️ チームメンバー&… 高崎市初心者の公式テニス🎾 一緒にやってくれる…
高崎市初心者の公式テニス🎾 一緒にやってくれる… 下豊岡町/…これから自転車始めたい方、初心者の方 …
下豊岡町/…これから自転車始めたい方、初心者の方 … 前橋市/前…草野球チームに所属されている方! 身体…
前橋市/前…草野球チームに所属されている方! 身体… 前橋市/前…今回久しぶりに卓球をやることにしました!…
前橋市/前…今回久しぶりに卓球をやることにしました!… 高崎市チームを大きくしたく募集させていただいて…
高崎市チームを大きくしたく募集させていただいて… 高崎市野球サークル新メンバー募集! バッティ…
高崎市野球サークル新メンバー募集! バッティ… 高崎市ゴルフ仲間を増やしたい方、一緒に楽しくラ…
高崎市ゴルフ仲間を増やしたい方、一緒に楽しくラ… 高崎市こんにちは😊 スポーツサークルです!! …
高崎市こんにちは😊 スポーツサークルです!! …