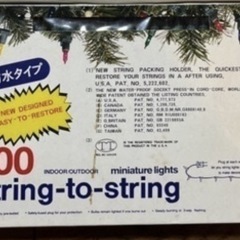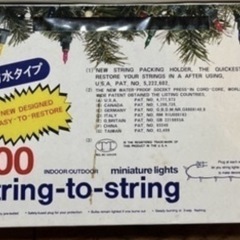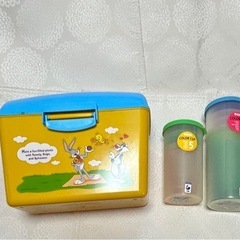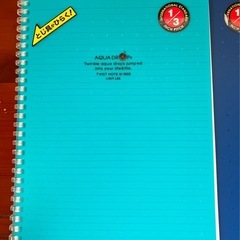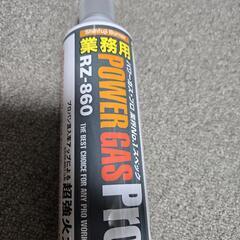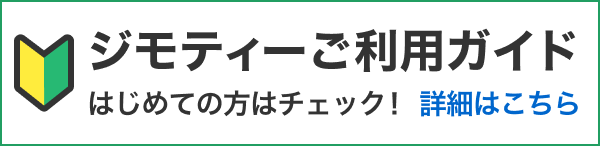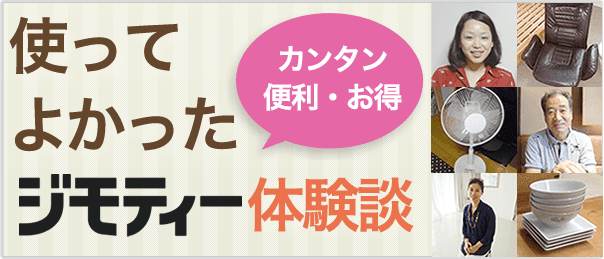- ジモティー
- 売ります・あげます
- 生活雑貨
- 家庭用品
- ガーデニング
- 東京都のガーデニング
- 板橋区のガーデニング
- 未使用 一輪挿し3点セット ①九谷焼 花柄 椿 ②草津 ③信楽焼
未使用 一輪挿し3点セット ①九谷焼 花柄 椿 ②草津 ③信楽焼(投稿ID : 1l2uqd)
未使用 一輪挿し3点セット ①九谷焼 花柄 椿 ②草津 ③信楽焼 サイズ約 ①最大幅8.5㎝ 高さ8㎝ ②最大幅8㎝ 高さ9㎝ ③最大幅9㎝ 高さ8.5㎝ 信楽焼とは、天平時代に生まれたと言われる日本六古窯の1つで、聖武天皇が紫香楽宮(しがらきのみや)を作る時に、瓦を焼いたのが始まりと言われています。 鎌倉時代中期には主に水瓶などが作られ、安土桃山時代には茶の湯の発達により、茶道具の生産が盛んになりました。茶器などの茶道具の名品が生まれ、信楽焼のわび・さびの味わいは現代にも生きています。 江戸時代は徳利や土鍋など、いろいろな生活用の器が作られ商業としても発達しました。 大正時代から戦前までは、各家庭で愛用された火鉢が多く製作されていました。明治時代には釉薬の研究と共に、信楽焼の火鉢は国内販売の8割を占めました。 土の味わいや温もりを生かした風合いが愛され、現在では、花器や食器、置物やタイルまで、幅広く住宅やインテリアに使われています。1976年(昭和51年)には信楽焼は国の伝統工芸品として指定され、狸の置物が代名詞にもなり「陶器の町、信楽」としても親しまれています 九谷焼(くたにやき)は、石川県南部の金沢市、小松市、加賀市、能美市で生産される、色絵の磁器。五彩手(通称「九谷五彩」)という色鮮やかな上絵付けが特徴である。 江戸時代、加賀藩支藩である大聖寺藩領の九谷村(現在の石川県加賀市)で良質の陶石が発見されたのを機に、藩士の後藤才次郎 [3]を有田へ技能の習得に赴かせ、帰藩後の明暦初期(1655年頃)、藩の殖産政策として始められたとされる。しかし、約半世紀後の元禄末期(1700年代初頭)に突然、廃窯となる。廃窯の理由は諸説あり、判然としていない。この頃に作られたものを「古九谷(こくたに)」と呼ぶ。 まとめ販売もしております たくさん出品しております! 是非ご利用ください❗️
ガーデニング(家庭用品)の売ります・あげますの関連記事
未使用 一輪挿し3点セット ①九谷焼 花柄 椿 ... 東京 中古あげます・譲りますを見ている人は、こちらの記事も見ています。
ぶるちゃんさんのその他の投稿記事:
- ジモティー
- 売ります・あげます
- 生活雑貨
- 家庭用品
- ガーデニング
- 東京都のガーデニング
- 板橋区のガーデニング
- 未使用 一輪挿し3点セット ①九谷焼 花柄 椿 ②草津 ③信楽焼