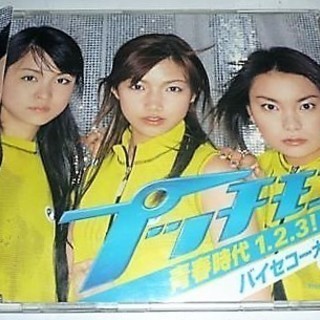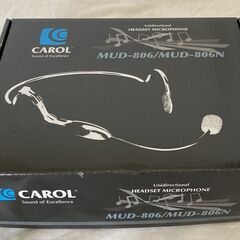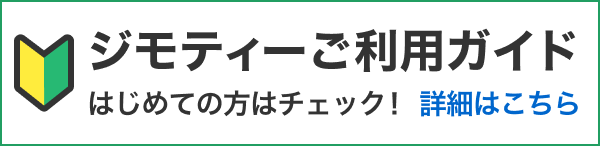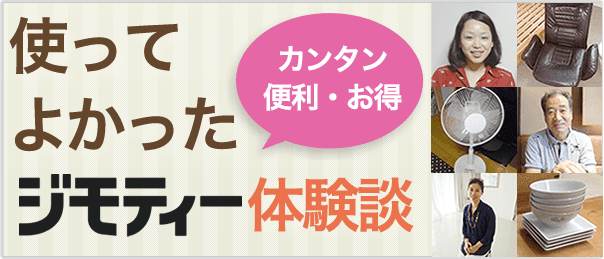- ジモティー
- 売ります・あげます
- 生活雑貨
- 家庭用品
- キッチン雑貨
- 神奈川県のキッチン雑貨
- 横浜市のキッチン雑貨
- ☆景春窯 ヤマニ陶器株式会社 四季菜鉢 3030125 灰釉ペアードレッシング入◆食卓グレードをアップする
☆景春窯 ヤマニ陶器株式会社 四季菜鉢 3030125 灰釉ペアードレッシング入◆食卓グレードをアップする(投稿ID : 1d5djy)
☆景春窯 ヤマニ陶器株式会社 四季菜鉢 3030125 灰釉ペアードレッシング入◆食卓グレードをアップする ●写真に写っている物が全てです。 ●大小ペアードレッシング入れです。 食卓にドレッシングやタレをそのまま置く方も多いと思います。 それをこの容器に入れて食卓に置くだけで一気にテーブルが映えるのではないでしょうか。 おもてなしの際などにも良いと思います。 ぜひこの機会にご検討よろしくお願いいたします。 ●灰釉とは草木の灰を溶媒とした釉薬のことです。 灰釉の種類はその原料となる草木が多く、多少の相違はあるが、イス灰類・土灰類・藁灰類と大きく3つに分類することができます。 イス灰類は、主に灰をつくる目的で草木を焼いたものなので、比較的鉄分が少なく使用釉薬は白色に近くわずかに淡青磁調で、染付の釉薬として適しています。 土灰類は、薪材の使用後に得た雑木の灰で、土石・鉄分などが混入しやすく非常に不純です。 その釉薬は、酸化焼成では黄褐色になり、還元焼成では淡青緑ないし褐色を帯びた緑色になります。 藁灰類は、珪酸質草木の灰類で、稲の藁を焼いたのち粉砕・水簸したもです。 藁灰は通常真っ黒で炭粉のようです。 一般には、土灰と混合して乳白色の不透明光沢釉として使用されます。 日本の焼き物の歴史を見ると、5世紀ごろの古墳時代に、より高温で焼くために“窯”が使用されるようになりました。 窯に木をくべると、土器の表面に自然と灰が降り注ぎ、火の中で灰が溶けて、ガラス質のものに変わっていきます。 これが自然釉の始まりです。 自然釉でコーティングされた陶器は、水を通しにくく、耐久性が大きく向上しました。 平安時代になると、灰を調合して「釉薬」をつくる技術が生まれ、後に「灰釉(かいゆう/はいゆう)」と呼ばれるようになりました。 灰釉は、陶器の耐久性を上げるとともに、多様な表情を生み出しました。 その後、日本六古窯(古来の陶磁器窯のうち、中世から現在まで生産が続く代表的な6つの窯、すなわち越前、瀬戸、常滑、信楽、丹波、備前の総称)を初めとして、千年以上にわたり、釉薬の技術が醸成されていきました。 焼き物の世界では、「一窯、二土、三細工」という言葉があります。 同じ土を使い、同じ装飾、同じ施釉をしたとしても、最後の“窯”の中で表情はまったく違ってきます。 火の当たり具合、火の通った道など、人間の手ではどうしようもない“窯の仕業”によって、“ゆらぎ”という魅力が生み出されるのです。つまり、釉薬はそれ単体ではなく、火や土と掛け合わさることでより深い味わいが生まれると言えます。 ●サイズ 大:最大幅20cm×高さ7cm 小:最大幅13cm×高さ4.4cm ● 取りに来られる方は対応できる日とできない日がございますので、あらかじめ日時をお知らせください。 基本的に午前中は対応できません。 ● 神奈川県内の方はご希望でしたら2,000円で配達も致します。 日時等はお互い都合の良いところを合わせていただく事となりますので、○日の○時に来てください、というのは基本的には受け付けられません。 ○日は無理というのも発生しますし、お伺いできる日も○時から○時の間で、という形になります。
キッチン雑貨(家庭用品)の売ります・あげますの関連記事
☆景春窯 ヤマニ陶器株式会社 四季菜鉢 3030... 神奈川 中古あげます・譲りますを見ている人は、こちらの記事も見ています。
ロボコンさんのその他の投稿記事:
- ジモティー
- 売ります・あげます
- 生活雑貨
- 家庭用品
- キッチン雑貨
- 神奈川県のキッチン雑貨
- 横浜市のキッチン雑貨
- ☆景春窯 ヤマニ陶器株式会社 四季菜鉢 3030125 灰釉ペアードレッシング入◆食卓グレードをアップする